保守契約は必要?ホームページ運用を安定させるポイント
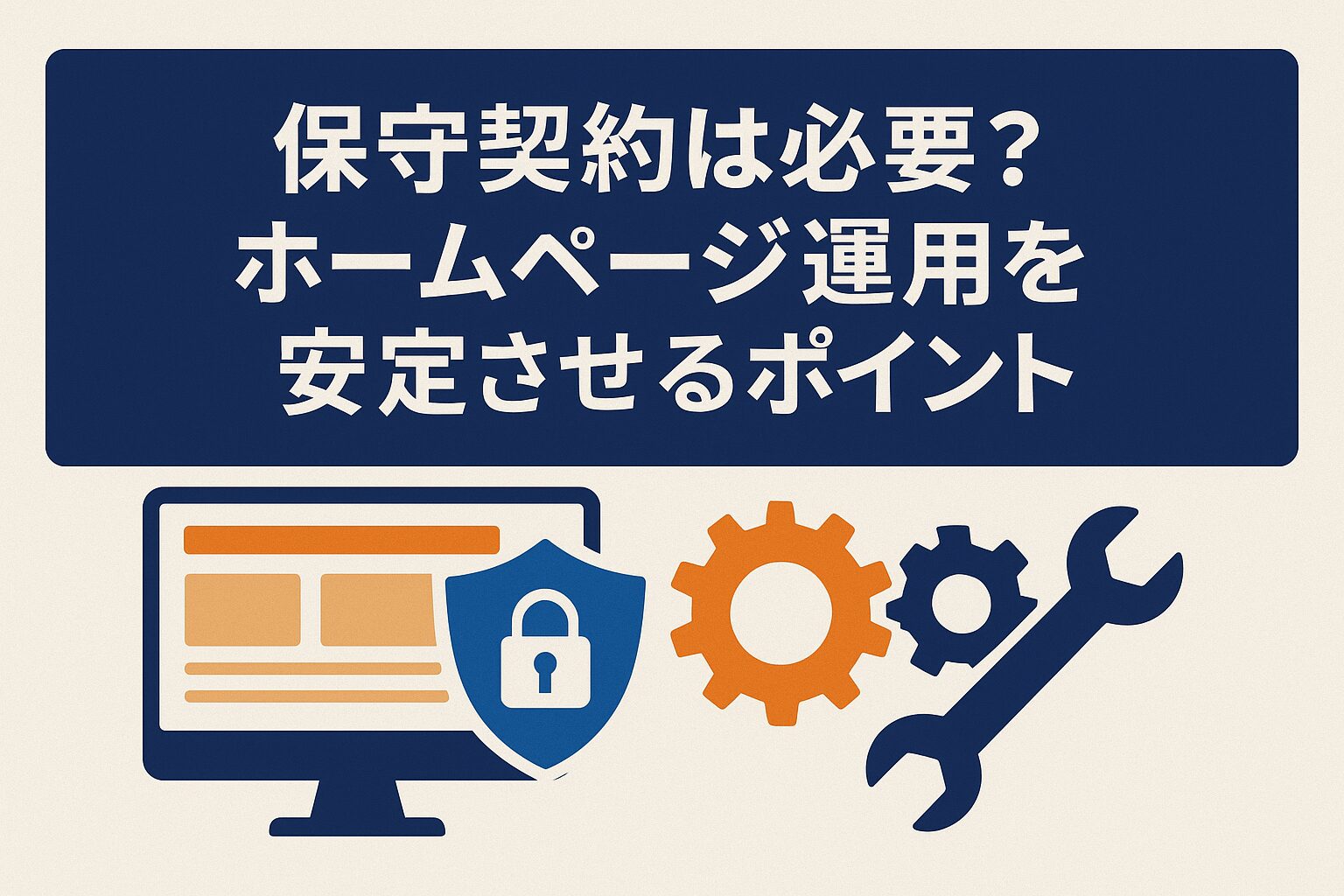
「ホームページの保守って本当に必要なの?契約しないとどうなる?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
実は、ホームページは「作って終わり」ではなく、公開後も継続的な管理が必要です。
放置したままだと、表示崩れ・ウイルス感染・トラブル時の復旧不能といった深刻なリスクに直面する可能性も──。
本記事では、営業歴10年・鳥栖市を拠点とするホームページ制作会社が、保守契約の必要性と判断基準を、初心者にもわかりやすく解説します。
■本記事でわかること
- ホームページ保守の定義と必要性の理由
- 実際に行われる保守作業と費用の相場
- 保守契約を結ぶかどうかの判断ポイント
■この記事の信頼性
筆者は、10年以上にわたり中小企業のWEB運用を支援してきた制作者です。
日々の保守・トラブル対応を行う現場視点から、具体的なノウハウを提供しています。
本記事を読むことで、あなたのホームページに保守契約が必要かどうかが明確になります。
読み終えるころには、「契約する・しない」の判断だけでなく、何を基準に外注を選べばよいかも理解できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
ホームページ保守とは?定義と基礎知識
ホームページ保守とは何か
ホームページ保守とは、WEBサイトを安全かつ安定的に運用し続けるために必要な「管理・点検・更新」などの継続的な作業を指します。主な内容には、ドメイン・サーバーの管理、CMSやプラグインのアップデート、セキュリティ対策、トラブル対応などが含まれます。ホームページは一度作って終わりではなく、運用開始後も継続的な管理が求められる“資産”です。特にWordPressのようなCMSを利用している場合、セキュリティ脆弱性への迅速な対応が重要となるため、保守は欠かせない業務となっています。
WEBサイトを放置することの危険性
WEBサイトを長期間放置すると、次のようなリスクが高まります。
- サーバー障害やシステムエラーの発見が遅れ、長時間のダウンに繋がる
- CMSやプラグインのバージョンが古くなり、脆弱性を突かれて不正アクセスを受ける
- Googleなどの検索エンジンからの評価が下がり、検索順位が低下する
- スマートフォンや新しいブラウザで正しく表示されなくなる
実際、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表している「情報セキュリティ10大脅威」では、CMSの脆弱性を突いた攻撃が毎年上位にランクインしており、保守されていないWEBサイトが被害を受ける事例が多数報告されています。
保守が必要となる背景
ホームページ保守の必要性は、主に「セキュリティ」「信頼性」「技術進化」など複数の要因から生まれています。
- サイバー攻撃の増加:個人情報や業務情報を狙った攻撃が増えており、日々のセキュリティ対策が求められます。
- 技術の進化:HTML、CSS、JavaScript、PHPなどの仕様が年々進化しており、古い構成のままでは正しく表示されないことがあります。
- ユーザー体験の重要性:更新されていない情報や不具合のあるサイトは、企業の信頼を損なう原因になります。
さらに、スマートフォンやタブレットの普及により、複数デバイスへの対応が求められる現代において、定期的な動作確認・改善は企業のオンライン戦略における基盤ともいえる存在です。
ホームページ保守で実施される主な作業内容
ドメイン・サーバー・SSLの管理
ホームページの基本インフラであるドメイン(URL)やサーバーは、契約の更新漏れや設定ミスによって突然サイトが見られなくなるリスクがあります。SSL証明書も同様に、期限切れのまま放置すると「この接続は安全ではありません」と表示され、ユーザー離脱に直結します。こうした基盤管理は保守作業の中でも最重要項目です。
CMSやプラグイン、PHPなどのバージョンアップ対応
WordPressのようなCMSでは、本体やプラグイン、テーマが頻繁に更新されます。これらを放置すると、古いバージョンにセキュリティホールが残り、不正アクセスの原因になります。また、PHPのバージョンが古いと正常に動作しないこともあるため、定期的なバージョンアップが必要です。
セキュリティ対策(不正アクセス・脆弱性対応など)
保守契約では、WAF(Web Application Firewall)やログ監視、不審アクセスの遮断などのセキュリティ対応も行います。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の報告では、CMSの脆弱性を突いた攻撃が年々増加しており、個人情報漏洩や改ざんといった深刻な被害も発生しています。
バックアップ・復元対応
サイトに不具合が生じた場合に備えて、定期的なバックアップを自動化するのも保守業務の一環です。万が一サーバーがクラッシュしたり、誤操作でデータを消してしまっても、バックアップから迅速に復元できます。これにより、業務の中断や信用喪失を防げます。
コンテンツの修正・更新
企業情報やスタッフ紹介、ブログ記事の修正など、日常的な更新作業も保守契約に含まれることがあります。特に採用情報や商品情報など「更新が多いページ」は放置するとユーザーに誤解を与えるため、定期的な見直しが求められます。
アクセス解析・改善提案
GoogleアナリティクスやSearch Consoleなどの解析ツールを用いて、サイトのアクセス状況を定期的にチェックし、改善提案を行うのも保守の一部です。例えば「特定ページの直帰率が高い」「スマホからのアクセスが多い」といった情報を元に、構成やUIの見直しを提案できます。
新しいブラウザや端末への対応
新しいOSやブラウザが登場すると、これまで表示されていた内容に崩れが生じることがあります。とくにスマートフォンの機種依存による表示不具合はユーザーの離脱を招きやすいため、都度検証と調整を行う保守が重要です。
トラブル時の対応・障害復旧
「画面が真っ白になった」「メールが届かない」といった緊急トラブルが発生した場合に、迅速に対応・復旧してくれるのが保守契約の大きなメリットです。特にECサイトや予約システムなど、稼働停止が売上に直結する業種では欠かせない体制です。
メールフォームやECサイトなど機能の点検
問い合わせフォームやショッピングカートなどの機能が正常に動作しているかを、定期的にチェックすることも保守内容に含まれます。知らないうちにメールが届いていなかったり、注文が入らないトラブルを未然に防ぐための重要な作業です。
ホームページ保守が必要な理由とそのメリット・デメリット
信頼性・セキュリティの維持
ホームページを常に安全で信頼性の高い状態に保つためには、保守が不可欠です。特に企業のホームページは、顧客に対する「顔」のような存在であり、表示不具合やセキュリティ事故が発生すると、ブランドイメージの低下や信頼損失につながります。たとえば、SSL証明書の期限切れにより「この接続は安全ではありません」と表示された場合、ユーザーは離脱してしまいます。
実際に、情報処理推進機構(IPA)が発表する「情報セキュリティ10大脅威」でも、CMSやウェブサイトを狙った攻撃が上位に挙げられており、未保守のサイトは狙われやすいとされています。
バージョンアップ未対応による表示崩れや不具合の防止
ホームページを構成するCMS(WordPressなど)、プラグイン、PHPなどは日々アップデートされています。これらを更新せず放置すると、ある日突然「サイトが真っ白になる」「画像が表示されない」といった不具合が発生することがあります。特にブラウザやスマートフォンの仕様が変わると、過去のHTMLやCSSでは対応できず、レイアウト崩れの原因になります。
更新作業を継続して実施することで、最新環境にも対応した見やすく安全なサイトを維持できます。
最新技術への対応
ホームページの技術は常に進化しています。たとえば、ページ表示速度を高速化する「WebP画像」や「Lazy Load(遅延読み込み)」といった手法、またモバイルファーストの設計など、最新技術に対応することでSEO効果やユーザー体験(UX)が向上します。
保守契約を結ぶことで、こうした技術的なトレンドにも対応できる体制が整い、競合に遅れをとらないWEB戦略を実現できます。
自社対応との比較:メリット・デメリット
| 対応方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自社で保守 | 費用を抑えられる | 専門知識が必要 トラブル対応が遅れる可能性 |
| 外部に委託 | 専門家の対応で安心 最新の技術・セキュリティに対応 |
月額費用がかかる |
技術者が社内にいない、もしくは兼任での対応が難しい場合は、外注した方が結果的にリスクを回避できるケースも多く見られます。
保守しない場合のリスク
- セキュリティ事故によりサイトが改ざん・停止される
- 問い合わせフォームの不具合で顧客の声を受け取れない
- バージョン未更新でページが崩れ、閲覧者の離脱が増える
- Googleの評価が下がり、検索順位が低下する
たとえば、ある中小企業が保守を行わずに放置していたところ、知らぬ間にウイルスを埋め込まれ、顧客にウイルスをばらまく事態になったという事例もあります。これは刑事責任や損害賠償にも発展しかねない深刻な問題です。
このように、保守を怠ることで発生するトラブルは、最終的に信頼・売上・安全すべてに悪影響を及ぼします。だからこそ、定期的な保守契約が必要不可欠なのです。
ホームページ保守契約を結ぶべきか判断するポイント
CMSの利用有無や技術的な難易度
WordPressのようなCMSを使用している場合、定期的なバージョンアップやプラグイン更新、セキュリティ対策が必要になります。これらの操作は一見簡単に見えても、相性の悪いプラグイン同士が原因で不具合が発生することもあり、ある程度の専門知識が求められます。
一方、静的なHTMLサイトなどは更新頻度が低ければ保守の必要性は限定的です。しかし、いずれにせよ「技術的な難易度」を判断基準として、保守契約を検討することが重要です。
自社で対応できる体制があるか
ホームページ保守を自社で行うには、以下のような体制が必要です。
- ITやWebに関する知識を持つスタッフが在籍している
- トラブル発生時に迅速に対応できる環境がある
- 業務としての優先順位や時間が確保できる
たとえば、社内にWeb担当者が一人だけの場合、その方が退職・休職するだけで保守が機能しなくなるリスクがあります。逆に、保守会社に契約していれば継続的なサポートを受けられる安心感があります。
保守を外注する場合のコストと工数比較
「社内対応」と「外注」のどちらがコストパフォーマンスに優れているかは、業務量やトラブル発生頻度によって異なります。以下のように比較してみましょう。
| 項目 | 自社対応 | 外部委託 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 不要 | 必要な場合あり |
| 月額コスト | 人件費に含む | 5,000〜50,000円 |
| 対応スピード | 即時対応可 | 契約内容により変動 |
| 技術力 | 担当者に依存 | 専門スタッフが対応 |
自社での対応に限界を感じる場合や、工数を削減したい場合は、外注の方がトータルコストを抑えられることもあります。
契約期間・解約・対応範囲などの確認
保守契約を結ぶ際には、内容をしっかり確認することが大切です。特に以下のポイントに注意しましょう。
- 契約期間:月契約か年間契約か
- 解約条件:途中解約は可能か、違約金の有無
- 対応範囲:どこまでが基本サービスか、どこからが有料対応か
- 緊急対応:トラブル時のサポート体制や連絡手段
たとえば、ある企業では保守契約を結んでいたものの、災害時に連絡が取れず復旧までに数日かかったという事例もあります。契約内容の詳細を確認し、信頼できるパートナーを選ぶことが大切です。
まとめ|ホームページ保守契約の必要性とは?
ホームページは「作って終わり」ではなく、継続的な保守があってこそ安定運用が実現します。サーバー管理やセキュリティ対策、トラブル対応など、放置によるリスクを避けるためにも保守契約は重要です。以下のポイントを押さえ、契約の必要性を正しく判断しましょう。
- 1. 保守契約で安全性を確保
- 2. 放置は信頼低下や機会損失に直結
- 3. 作業内容と費用の内訳を把握
- 4. 自社対応か外注かを比較検討
- 5. 契約書の内容を必ず確認
- 6. 自分で対応する場合は注意が必要
中小企業にとっても、適切な保守は業務効率やブランド価値の維持に直結します。まずは実績ある保守会社へ相談し、自社に合ったプランを選びましょう。