ホームページ制作費用の内訳を徹底解説!費用相場も紹介
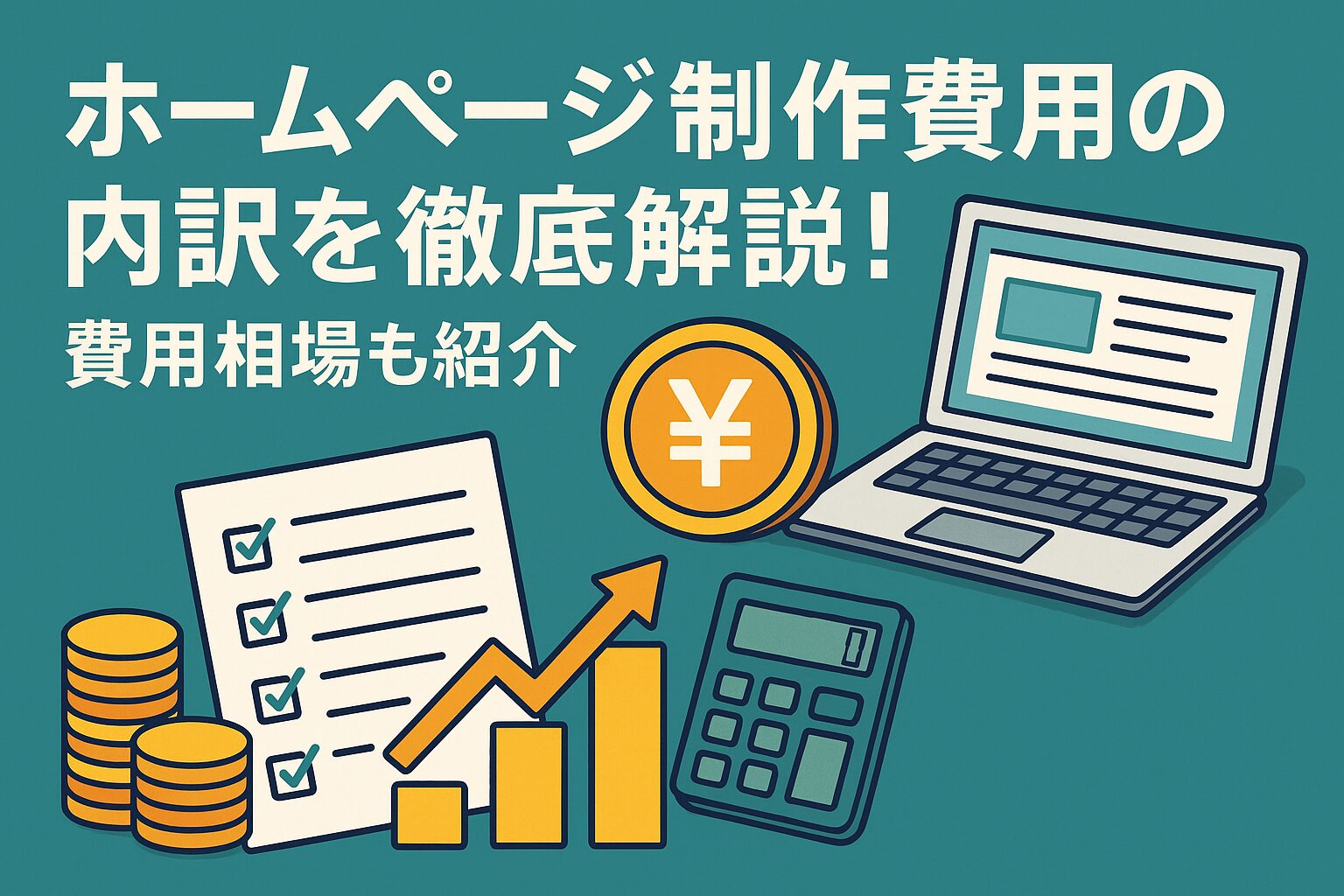
「ホームページを作りたいけど、費用相場が全くわからない」
「見積もりをもらったけど、この内訳は妥当なの?」と悩んでいませんか?
そんなお悩みを持つ方に向けて、本記事ではホームページ制作費用の相場と内訳を徹底的に解説します。
■本記事を読むと得られること
- 1. ホームページ制作の目的別・依頼先別・サイト種類別の費用相場がわかる
- 2. ディレクション費から保守費まで、項目ごとの費用内訳と内容が理解できる
- 3. 費用を抑えるための具体的なコツや補助金活用法がわかる
■本記事の信頼性
本記事は、営業歴10年、鳥栖市を拠点とするホームページ制作会社として、多数のWebサイトを制作してきた実績をもとに執筆しています。中小企業の予算や目的に合わせた最適な制作プランを提案してきた経験を活かし、初心者の方にもわかりやすく解説しています。
ホームページ制作の費用を正しく把握し、無駄なく、目的に合ったサイト作りを成功させるための知識を身につけられる内容になっています。最後まで読むことで「納得できる価格でホームページを作る方法」がわかり、自信を持って依頼・制作を進められるようになります。
ホームページ作成費用の相場・目安
目的別の費用相場
ホームページ制作費用は「集客」「採用」「ブランディング」など目的によって大きく変わります。例えば、集客を目的としたホームページはSEOや広告運用も必要になるため、初期費用50万円〜150万円程度が一般的です。採用専用サイトの場合は20万円〜80万円、名刺代わりのシンプルな会社案内サイトであれば10万円〜30万円で制作可能です。
総務省「情報通信白書2023」によると、企業のホームページは目的に応じて制作予算を確保しており、売上や規模に比例して費用が増加する傾向があります。
実際に地方中小企業C社では、採用を強化するために60万円の予算で採用専用サイトを制作し、採用エントリー数が前年比200%に伸びました。
このように、目的を明確にすることで必要な機能が判断でき、無駄のない費用配分が可能になります。
依頼先別の費用相場(制作会社・フリーランス・自作)
制作を依頼する先によって費用は大きく異なります。制作会社の場合は30万円〜200万円、フリーランスは10万円〜80万円、自作は初期費用0〜5万円程度で済むケースが多いです。ただし自作は時間やスキルが必要で、ビジネスチャンスを逃すリスクもあります。
中小企業庁の「中小企業白書2022」でも、ホームページを制作会社に依頼した企業は成果を出しやすい傾向にあると報告されています。
実際に小売業D社は自作サイトで半年間運用後、問い合わせが増えなかったため制作会社に依頼し、80万円でリニューアルして売上が1.5倍に改善しました。
予算だけでなく、依頼先のサポート体制やスキルも含めて総合的に検討することが重要です。
サイト種類別(コーポレート、LP、ECなど)の費用相場
サイトの種類ごとに費用は大きく異なります。コーポレートサイトは20万円〜100万円、ランディングページ(LP)は10万円〜50万円、ECサイトは50万円〜300万円が相場です。特にECサイトは商品点数や決済機能により費用が高額になる傾向があります。
JETRO(日本貿易振興機構)の「越境ECに関する調査2021」によると、ECサイト制作は小規模でも50万円以上かかるケースが多く、デザインや機能性で費用が変動するとしています。
例えば飲食店E店はLPを30万円で制作し、キャンペーンページとして活用して集客効果を高めました。
サイト種類に合わせて機能やボリュームを検討することが、適切な費用感を知るポイントです。
サイト規模別(ページ数など)の費用相場
ページ数が増えるほど費用は上がります。5ページ以下の小規模サイトは20万円〜50万円、10〜20ページ規模の中型サイトは50万円〜150万円、50ページ以上の大型サイトは200万円を超えるケースもあります。
経済産業省「デジタル化支援施策ガイド2022」でも、規模に応じたコスト感を提示しており、ページ単価は平均2万円〜5万円程度とされています。
実例として、製造業F社は15ページの中型サイトを100万円で制作し、取引先からの信用度が向上しました。
サイトボリュームは企業規模や掲載情報量に合わせて計画しましょう。
制作方法別の費用相場
オリジナルデザインで制作する場合は50万円以上、テンプレートを活用すれば10万円〜30万円程度に抑えられます。最近はノーコードツールも普及し、自作でも安価に作成できるようになっていますが、自由度は低めです。
実例として、個人経営の美容院G店は20万円でWordPressテンプレートを利用し、費用を抑えつつデザイン性の高いサイトを実現しました。
制作方法を選ぶ際は、デザインや機能の自由度と費用のバランスを考慮しましょう。
制作会社の違いによる費用の差
大手制作会社はノウハウや実績が豊富な一方、管理費や人件費が上乗せされ50万円〜300万円になることもあります。地元の中小制作会社や個人事業主に依頼すれば30万円前後で制作可能な場合も多いです。
中小企業庁の「IT導入補助金活用状況(2022)」では、地域密着型の制作会社に依頼して費用を抑えた中小企業が多数紹介されています。
例えば商社H社は、地元の制作会社に依頼して70万円で作成し、サポートを受けながら運用改善まで進めることができました。
制作会社の規模や得意分野を比較し、自社に合ったパートナーを見つけることが費用を最適化する鍵です。
ホームページ制作費用を決める要素
サイトボリューム・ページ数
ホームページのページ数は制作費用を決定する重要な要素です。5ページ以下なら20万円〜50万円、10ページを超えると50万円〜150万円になるケースが多いです。ページごとに必要なデザイン・コーディング作業量が増えるため、単純にページ数が多いほど費用は比例して上がります。
経済産業省「IT導入状況調査2023」では、ページ単価は平均で2万円〜5万円とされており、ページボリュームが費用に大きく影響すると報告されています。
実例として、建設業J社は15ページ構成のホームページを120万円で制作し、詳細なサービス紹介ページを設けることで商談率を30%向上させました。
ページ数は費用の見積もりに直結するため、必要最低限に絞ってからボリュームを拡張していく方法も有効です。
機能・開発要件の有無
予約フォームや会員機能、決済機能などのシステム開発が必要かどうかも費用を左右します。これら機能は10万円〜100万円以上追加されることがあります。特にECサイトや大規模ポータルは開発費が高額になる傾向です。
中小企業庁「中小企業白書2022」でも、機能追加により費用が平均1.5倍になる例が紹介されています。
例えば、美容室K店は初期の基本サイトに加え、オンライン予約機能を追加実装した結果、費用は70万円から110万円に増えましたが、予約件数は2倍になりました。
必要な機能を精査し、不要な機能を削減することで予算を最適化できます。
納期
短納期を希望する場合、急ピッチで作業する必要があり追加費用が発生します。通常2〜3ヶ月かける制作を1ヶ月以内にする場合、費用が20%〜50%増しになるケースも珍しくありません。
実際に飲食店L店は、急ぎで開業日までに公開したいとの要望で、通常見積もり50万円のところ、短納期対応費としてプラス20万円が加算されました。
スケジュールに余裕を持つことで、費用負担を抑えることが可能です。
制作会社や制作者の技術力・実績
有名な制作会社や経験豊富なデザイナーに依頼すると、技術料として相場より高くなることがあります。実績のある制作会社では安心感や品質が担保される反面、費用は30万円〜100万円以上上乗せになる場合があります。
JETRO「IT市場動向レポート2022」によると、実績豊富な会社と実績の少ない会社で平均40万円以上の費用差が出る傾向が確認されています。
例えば、老舗制作会社に依頼した小売業M社は180万円で制作しましたが、オリジナルデザインやブランディングが評価され、展示会での新規取引につながりました。
予算と期待するクオリティのバランスを見極め、依頼先を選定しましょう。
目的と戦略の整理
ホームページ制作の目的と戦略が曖昧だと、修正や追加要望が増えて費用が膨れ上がることがあります。目的を最初に整理し、必要なコンテンツや機能を明確にすることが費用を抑える鍵です。
総務省「情報通信白書2023」でも、戦略設計を先に行った企業は、平均15%程度制作費を抑えられる傾向があると報告されています。
例えば、不動産業N社は制作前に「物件問い合わせを増やす」という目標を明確にし、LP中心の構成で50万円に費用を抑えつつ、問い合わせ件数を3倍に増やしました。
目的と戦略を整理することで、予算を効果的に使い、費用対効果の高いホームページ制作が可能になります。
メリット・デメリット比較(外注・自作・個人依頼)
制作会社に依頼するメリット・デメリット
制作会社に依頼する最大のメリットは、デザイン・開発・SEO対策までワンストップで対応できる点です。専門知識や経験を活かし、高品質なホームページを制作できます。修正対応や保守サービスも充実しているため、完成後も安心です。一方でデメリットは、費用が高くなること。一般的に50万円〜200万円以上かかる場合が多く、打ち合わせも複数回必要で工期が長引くこともあります。
総務省「情報通信白書2023」によると、制作会社に依頼した企業の65%が「期待以上の成果が得られた」と回答しています。
実例として、製造業O社は制作会社に120万円でコーポレートサイトを依頼し、公開3ヶ月で問い合わせ数が月平均15件から40件に増加しました。
制作会社は「手厚いサポート」と「高品質な制作」が欲しい場合に適していますが、予算に余裕を持つ必要があります。
フリーランスに依頼するメリット・デメリット
フリーランスは費用を抑えつつ、柔軟な対応を期待できる点がメリットです。制作会社に比べて中間マージンが不要な分、10万円〜80万円程度で依頼できることが多く、個別の要望にも親身に対応してくれるケースが少なくありません。ただしデメリットとして、納期の遅延リスクや保守サービスが限定的な場合があり、フリーランスのスキルや実績によって仕上がりに差が出やすい点が挙げられます。
中小企業庁「中小企業白書2022」でも、フリーランス依頼は価格優位性が高い一方、トラブル事例も一定数あると指摘されています。
実際に美容院P店は、フリーランスに30万円でサイトを依頼し、開業日に合わせて納品され、早期に集客をスタートできました。
フリーランスは「コストを抑えたい」「小規模サイトを作りたい」場合に適していますが、実績確認を必ず行いましょう。
自分で作成するメリット・デメリット
自作のメリットは費用を大幅に抑えられる点です。テンプレートやノーコードツールを使えば初期費用数千円〜数万円で済むこともあります。自分で自由に更新でき、知識が身につくのも魅力です。しかし、デメリットは時間がかかることと、デザインや機能面での完成度が低くなるリスクです。SEO対策や保守なども自分で行う必要があるため、ビジネスチャンスを逃す可能性もあります。
JETRO「IT市場動向レポート2022」によれば、自作サイトで集客に苦戦した企業が多いことが報告されています。
実例として、飲食店Q店は自作サイトで半年運用後、問い合わせがほとんどなかったため、制作会社にリニューアルを依頼し成果を改善しました。
自作は「費用を抑えて試したい」場合に選択肢になりますが、ビジネスでの成果を求めるなら慎重に検討しましょう。
実例・見積書例・調査結果
制作会社の見積書例
制作会社に依頼するとどのような費用構成になるかを知るために、実際の見積書例を紹介します。以下は中小企業向けコーポレートサイト(10ページ構成)の見積もり例です。
| 項目 | 金額(税別) |
|---|---|
| ディレクション・進行管理 | 150,000円 |
| デザイン(トップ+下層9ページ) | 300,000円 |
| コーディング(10ページ分) | 200,000円 |
| 問い合わせフォーム設置 | 50,000円 |
| スマホ対応(レスポンシブ) | 80,000円 |
| テスト・検証 | 30,000円 |
| 合計 | 810,000円 |
このようにディレクション費用が総額の約20%を占め、デザイン・コーディングが大部分を占めています。国土交通省「中小企業IT活用実態調査2022」でも、見積書には細かく項目を分けて提示する制作会社が増えていると報告されています。
例えば製造業R社は、このような見積もりでサイトを発注し、公開後3ヶ月で新規取引先を2社獲得しました。
見積書は内容を分解して確認し、不要な項目がないかチェックすることで、予算の無駄を防げます。
一般的条件での費用調査結果
総務省「情報通信白書2023」では、一般的な中小企業がホームページを制作した場合の平均費用は以下のように報告されています。
- 5ページ以下の小規模サイト:30万円〜50万円
- 10〜20ページ規模の中型サイト:50万円〜150万円
- 20ページ以上の大型サイト:150万円以上
また、サイトの種類や目的によっても相場は変わり、以下の傾向があります。
- 採用専用サイト:20万円〜80万円
- ランディングページ(LP):10万円〜50万円
- ECサイト:50万円〜300万円以上
例えば建設業S社は10ページ規模のコーポレートサイトを100万円で制作し、公開直後から取引先の信用度が上がったとの声がありました。
このように見積書例や統計データを参考にしながら、自社の予算感に合わせた費用計画を立てることが重要です。
まとめ|ホームページ制作費用を理解して賢く依頼しよう
ホームページ制作は、目的や規模、依頼先によって大きく費用が変わります。本記事では相場感や費用内訳を詳しく解説し、コストを抑える具体的な方法まで紹介しました。制作前に正しい知識を持つことで、無駄な出費を防ぎ、期待通りのホームページを実現できます。予算を立て、目的を整理してから見積もりを取り、納得できる形で制作を進めましょう。
- 目的で費用は変動
- 内訳で予算を把握
- 抑えるコツを活用
さらに詳しく知りたい方は、関連記事「外注と内製どっちが良い?ホームページ制作を比較」もぜひご覧ください。